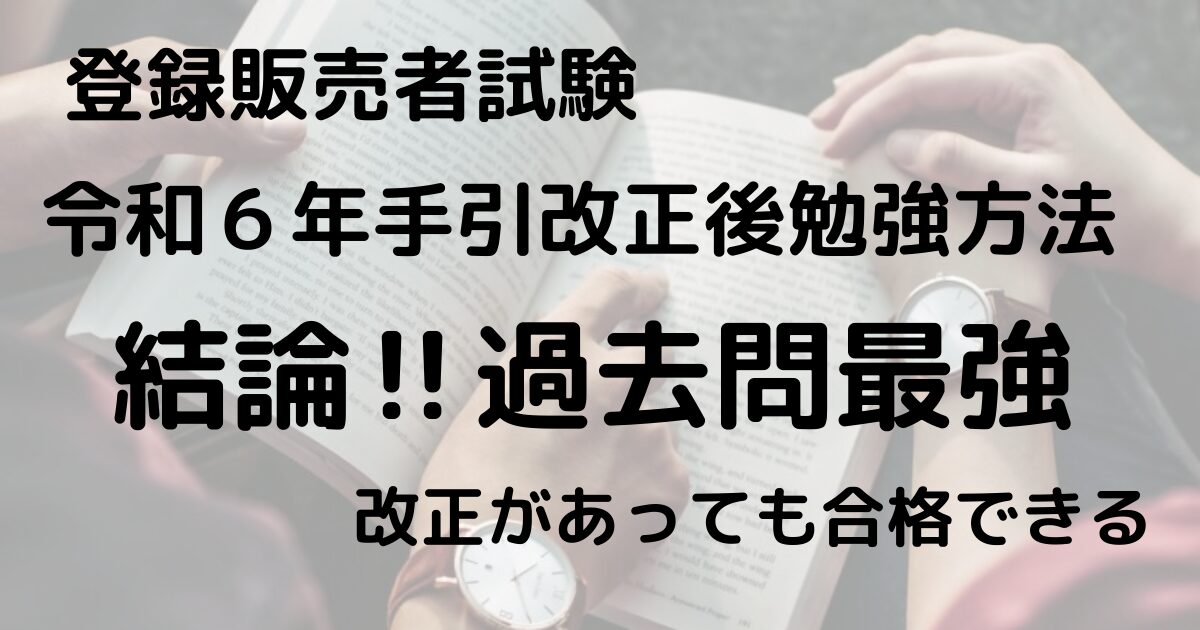登録販売者試験の問題は、厚生労働省のサイトで公開されている登録販売者試験問題作成に関する手引『通称手引』から出題されます。この手引は不定期に改訂され、今年2024年(令和6年)4月10日にも改訂が行われました。
これは3年連続の手引改訂となります。2022年3月と2023年にも改訂があったため、受験者の皆さんは不安を抱えていると思います。
しかし、安心してください。今年度の改訂内容は試験に大きな影響を及ぼすものではありませんでした。
この記事では改訂について以下のような内容で説明いたします。
- 変更点の概要: 今年度の改訂で何が変わったのか、具体的なポイントを紹介します。
- 受験者への影響: 改訂が受験者に与える影響について考察します。
- テキスト購入のタイミング:改訂があるなら、いつテキストを購入すべきかをアドバイスします。
- 効果的な勉強方法:改訂があった場合、どのような勉強が効果的か紹介します。
私は2016年から地方のドラッグストアで登録販売者試験受験者の講師をしています。
これまで5回の手引改訂を受験者と共に経験してきました。この記事では、改訂についての実践的なアドバイスをお伝えします。
変更点の概要: 今年度の改訂で何が変わったのか
2024年(令和6年)の最新版手引は厚生労働省のHPよりダウンロードできます。
今回の手引改訂では、試験内容の中心となる部分や最重要部分の変更点は、見受けられませんでした。
主な変更点は以下の通りです。
- 2章の剤形の表現が見直し、舌下錠が追加された。
- 3章で点鼻薬のステロイド性抗炎症成分に関する留意点が追加された。
- 4章別表4-1「医薬部外品の効能効果の範囲」の「その他医薬部外品」に消毒剤が追加された。
- 薬事・食品衛生審議会が『薬事審議会』となった。
- 4章別表4‐2「化粧品の効能効果の範囲」に注意書きが追加された。
- 5章別表5‐1「してはいけないこと」にデキストロメトルファンに関する注意事項が追加された。
手引変更点内容をくわしく解説
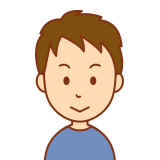
具体的には何が変わりましたか?
では以下改訂の内容を解説します。
2章:剤形の表現の見直し
2章の剤形の表現部分が見直されました。
これまでは、口の中で溶かした後にその成分を飲み込み、胃や腸で吸収され作用する内服の薬剤と、直接口の内で作用する薬剤(例えば口内炎パッチなども)が明確に表現されていませんでした。
| 改定前 | 改定後 |
| 口腔用錠剤 | 錠剤(内服) |
| ・口腔内崩壊錠 | ・口腔内崩壊錠 |
| ・チュアブル錠 | ・チュアブル錠 |
| ・トローチ、ドロップ | 口腔用錠剤 |
| 改定前は成分を内服するものと、口内で適用するものが明確に分かれていなかった。 | ・トローチ、ドロップ |
| ・舌下錠 |
シンプルに表現すれば、成分を飲みこんで使用する錠剤と、成分を口の中で使う錠剤で分けられたということです。
個人的には、追加された『舌下錠』あたりが出題されそうな予感がします。
舌下錠については使用方法を確認しておきましょう。
3章:点鼻薬のステロイド性抗炎症成分に関する留意点
3章は軽微な変更しかありませんでした。
その中でもし試験で出題されるとすれば、鼻に用いる薬(点鼻薬)にステロイド性抗炎症成分の記述が追加されてことでしょう。
特に、追加された記述の中で『ステロイド性抗炎症成分が配合されて いる場合には、長期連用を避ける必要がある。』とある部分が出題しやすそうに感じます。
4章:別表4-1「その他医薬部外品」に消毒剤が追加
4章はいくつか追加項目がありました。
4章に別表4-1「その他医薬部外品」という部分があるのですが、そこに『消毒剤: 物品の消毒・殺菌を目的とする消毒剤』というものが追加されました。
『物品の消毒』とは具体的には、哺乳瓶を消毒するような(ミルトンなど)ものが対象となります。
これについては、試験で出題されるかは微妙です…
4章:薬事・食品衛生審議会が『薬事審議会』となった
これまで厚生労働省に『薬事・食品衛生審議会』が設置されていました。
しかし、法整備により食品に関しては消費者庁に設置された『食品衛生基準審議会』が担当となり、薬事に関することは厚生労働省に設置された『薬事審議会』が受け持つことになりました。
この「薬事・食品衛生審議会」の内容は、改訂前の試験でたびたび出題されていたので、改訂後も出題される可能性が高いと考えます。
例えば、試験で以下のように出題された場合。
・厚生労働省大臣は薬事・食品衛生審議会に相談する→◯or✕
改訂前は◯で正解でしたが、改定後は✕で「薬事審議会」が正解となります。
4章:別表4‐2「化粧品の効能効果の範囲」に注意書きの追加
化粧品の効能効果の部分で注釈4として以下の通り追加がありました。
『乾燥による小ジワを目立たなくするについては、日本香粧学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。』
試験で出題されるかはわかりませんが、出題されても大丈夫なように確認しておきましょう。
5章:別表5‐1「してはいけないこと」にデキストロメトルファンが追加
『服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと』の懸念される症状「眠気等」の欄に『デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、フェノールフタリン酸デキストロメトルファン※鎮咳去痰薬のみ』と追加されました。
特に「※鎮咳去痰薬のみ」という部分を押さえておいてください。
手引改訂が受験者に与える影響
結論から言うと、手引が改訂されても受験者にあまり影響はありません。
改訂があると試験内容がガラッと変わってしまうのではないか?と不安になる方が多いと思いますが、そのようなとこはありません。
登録販売者試験は、120の問題で受験者がお客様に正しく薬を販売できる知識があるか?を確認する試験です、手引が改訂されたからと言って、改訂部分を優先的に出題したのでは、本来の試験の目的が達成されません。
以上のようなことから、実際の試験では、改訂部分が合否に関わるほど出題されることはありません。
改訂があっても今までの勉強は無駄にならない
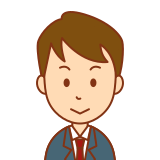
改訂で今までの勉強は無駄になりますか?
改訂があっても今までの勉強は無駄になりません。
120問の試験問題のうち、これまでの頻出問題は出題されます、またこれまで頻出問題となっていた内容が変更された場合は、高確率で出題されます。
改訂前にシッカリと勉強していた人は、変更内容を確認することで「ここが変わったんだな」「これが追加されたな」「これは過去問でもよく出題された部分だな」と出題されそうな部分がよく分かるはずです。
それより、頻出問題以外のイジワルな問題が出題される頻度が減り、改訂内容を知っているか確認するだけの素直な問題が多く出題されます。
実際に2023年に行われた登録販売者試験では、手引の改訂内容から出題された問題のほとんどが手引の文言をコピペしたような内容でした。
このように改訂直後の試験では、改訂の内容さえ知っていれば簡単に解けるラッキー問題が多くなります。
改訂箇所の確認は、YouTuberやテキストの出版社・通信講座スクールがネットなどで情報を発信してくれます。
これまで通りの勉強をしっかりと行った上で、このような情報を上手に使えば十分試験に合格できるはずです。
改訂があるならテキストはいつ買ったら良いの?
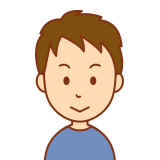
最新の改訂に対応したテキストを買ったほうが良いですか?
改訂版の出版を待たずに、登録販売者試験の勉強を始めようと思った時で手に入る最新版のテキストを買ってください。
たしかに手引の改訂があるとテキストの内容は変わってしまいます。
極端な場合、改訂前のテキストで正しかった内容も、改訂後では誤りになってしまう事もあります。
しかし、4月に改訂があった場合その内容に対応したテキストが出版されるのは、早くても6月~7月頃になります。
そのタイミングでテキストを買って勉強を始めたとしても、とても9月頃のにある試験に勉強が間に合いません。
令和5年もそうでしたが、改訂部分が試験問題となって出題される数はそれほど多くありません。
ですからテキストは、勉強を始めようと思った時に店頭で販売している最新版を購入し、1日でも早く勉強を始めることをおすすめします。
これから勉強を始めるためにテキストの購入を考えているのなら、私も使っている中央法規出版のものをおすすめします。
X(旧ツイッター)でも書いていますが、とにかくこのテキストは巻末の索引が良くできています。
勉強をしている時、成分名などを巻末の索引を使って調べようとしても、どこに載っているかわからなかったり、索引に載っていなくて時間ばかり過ぎてしまうことがあります?
中央法規出版のテキストなら索引に載っていないと言うことがほとんどありません。
それに、索引にはテキストに記載されているページが全て載っているので、2章の部分に載っている内容なのか3章?5章なの?という時も一度に確認することができて便利です。
わからない問題の内容がテキストのどこに書いてあるか見つけ出せず、時間ばかりかかってしまうという人はこちらのテキストがおすすめです。
登録販売者試験に合格するためには、手引改訂を気にせず少しでも早く勉強を始めることを優先してください。
改訂があったらテキストは買い直す?
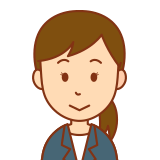
改訂があったらテキストを買い直したほうが良いですか?
すでに改訂前のテキストで勉強を進めているなら買い替える必要はありません。
どこの出版社でも出版後に手引の改訂が合った場合は、ホームページなどで正誤表などを公開します。
それを使って勉強をしておけば大丈夫です。
注意‼フリマサイトなどでテキストを購入する時は気をつけて
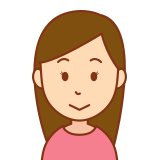
メルカリなんかでたくさん出品されていますが…
登録販売者試験のテキストを購入する時は、必ずその参考をがいつの手引に対応しているか確認してからにしてください。
特にフリマサイトなどでは古い平成30年版や平成28年版がかなりの量出品されています。(売れ残ってるだけかも)
最新版が出品されてもほとんど新品を購入する価格と変わらないか、お買い得なものはすぐに売れてしまいタイミング良く安く買うことができません。
また、友達から登録販売者試験のテキストをタダでもらえたとしても、それが最新の手引に対応していないものだった場合はデメリットしかありません。
価格や手間を考えると、書店やネットで最新版を購入するほうが間違いないと思います。
効果的な勉強方法:改訂があったら勉強方法はどうしたら良い?
手引の改訂があっても、今まで通り過去問をしっかり解いて頻出問題を確実に正答できるような勉強をしてください。
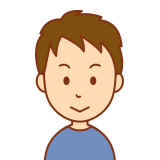
でも過去問はあてにならないのでは?
手引が改訂されても過去問が最強です。
も一度書きますが、登録販売者試験はたった120問の問題で受験者がお客様へ正しく安全に薬を販売できる知識があるかを確認する試験です。
『お客様へ正しく安全に薬を販売できる知識があるか』を確認する質問は頻出問題となります。
手引が改訂されたからといって、人の命に関わるかもしれない頻出問題を出題しないわけにはいきません。
ですから、まずは過去問をシッカリと解くことが基本となります。
また、過去問で頻出問題だった内容が変更された場合は確実に出題されます。
それに対応するためにも、どの問題が頻出問題なのか?過去問を解いて把握しておくことが重要です。
手引の改訂があっても、登録販売者試験は頻出問題と改訂があった内容の頻出問題が正答できれば、十分合格点数に達することができます。
改訂があった年のおすすめの勉強方法としては、複数の過去問を何度も解いて90点以上の点数が取れるようになってから手引の改訂部分を確認する方法です。
そうすれば、改訂内容のどれがこれまで頻出問題として出題されていたか把握できるはずです。
まずは過去問をシッカリ90点以上取れるように勉強しましょう。
現在、私の勉強会で一番使われているのはKADOKAWAより出版されている「これで完成! 登録販売者 全国過去問題集 2024年度版」です。
この過去問集のおすすめポイントは、解説部分ちょっとしたテキスト並みにくわしく記載されていることです。
時間がなくていちいちテキストを調べていられない人にピッタリの過去問集です。
手引改訂の間違った勉強方法
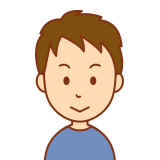
「これはやらないで」という勉強はありますか?
ついウッカリやってしまいがちな間違った勉強方法があります。
それは改修履歴入の手引から、変更点を片っ端から手持ちのテキストやノートに書き写す方法です。
厚生労働省の手引のサイトには『令和〇〇年◯月版からの改修履歴入』という手引のファイルがあります。
このファイルは、以前の手引から最新版の手引への変更があった箇所を、削除されたものには打ち消し線で、新しく追加された内容は青い文字で記載されているものです。
あまり登録販売者試験の事を知らない人は、この変更された打ち消し線や青文字を片っ端から自分の持っているテキストに書き加えるor ノートにまとめたら良いのでは無いか?と考えてしまいますが。
効率が悪いのでおすすめしません。
なぜなら、改修履歴入では、打ち消し線が引いてあっても削除になっているわけではなく、他の段落やページに文章が移動しているだけだったり、テニヲハや言い回しを変えただけで文章としてはあまり意味が変わっていなかったりするものが多く、これらを片っ端から書き写してもあまり意味がありません。
純粋な追加の青文字も大量にあリすぎるため、とても全てをテキストやノートに書き写す事は不可能で時間とモチベーションを無駄に消費するだけです。
もちろん試験に出そうな部分だけ書き出せれば良いのですが、これから登録販売者試験の勉強を始めよう言う人が、どの変更が試験に出そうで、どれがあまり出ないかは判断できません。
結局、無駄な時間と労力を消費することになってしまいます。
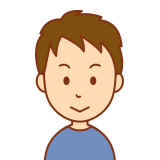
では改訂内容は無視して良いのですか?
無視して良いわけではありませんが、せめて前出の通り過去問を90点取れるぐらいになってから改訂内容を確認したほうが良いです。
そのぐらいに実力がついていれば、改修履歴入の手引に目を通した時に「あ、ここの記述こんな風に変わってる」とか「この成分が追加されてる」と気がつけるはずです。
それが難しいなら、ネットの情報サイトやYou Tubeでスクールの先生が解説している追加変更点だけ確認しておけば十分合格できるはずです。
まとめ
最後にまとめます。
- 改訂部分は合格に直接影響が出るよほど出題されません。
- テキストはその時点で最新のもので大丈夫です。
- 勉強方法はこれまで通り過去問をしっかりやり込んでください。
- 過去問が90点超えられるようになったら改訂部分をインターネットなどで確認しましょう。
手引の改訂が行われても受験者のみなさんは不安になる必要はありません。
過去問で何度も出題される基本的な問題がしっかり出来ていれば大丈夫です。
改訂部分ばかりに振り回されて、基本的な問題の勉強をおろそかにしてしまうと不合格になります。
改定部の情報は基本の問題の学習がある程度仕上がってから確認するようにしましょう。
過去問をしっかりと解けるようになれば必ず合格はできます。