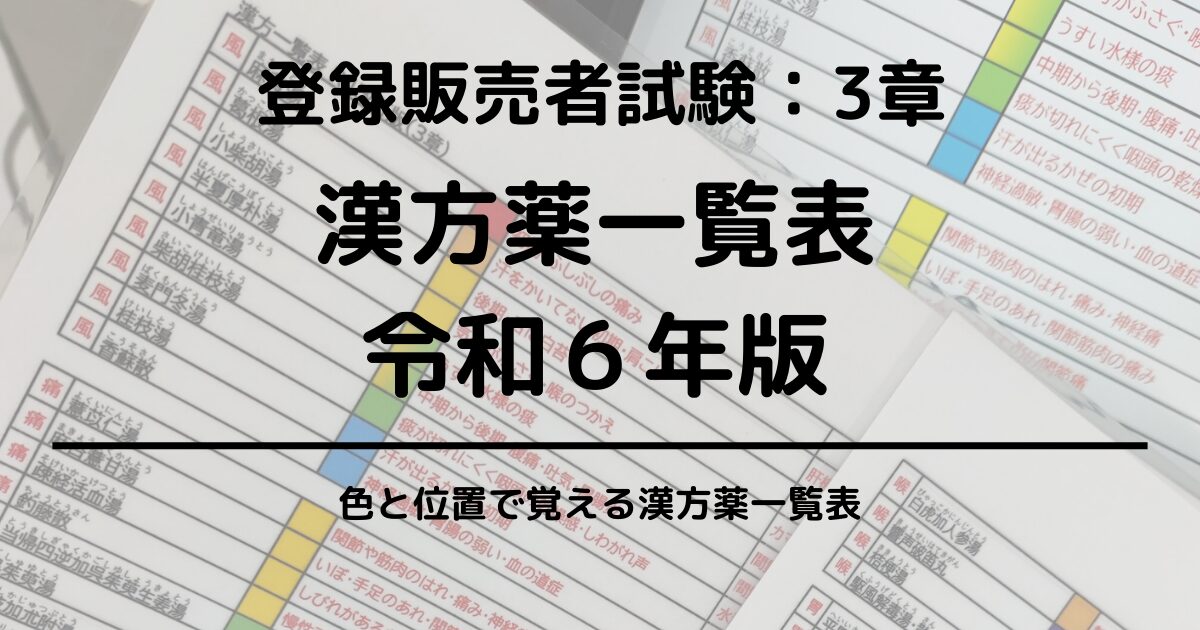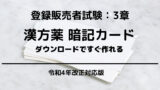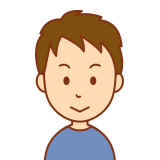
3章の漢方薬の勉強ムリかも。
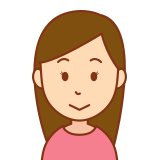
もう漢方薬はあきらめようかな。
登録販売者試験の勉強で3章の漢方薬がニガテな人が多いですよね。
少し前に登録販売者試験に合格した人の中には「漢方は全部捨てても大丈夫」と言う人もいますが、最近の登録販売者試験では、3章での漢方薬の出題率が確実に増えています。
!いったいどうしたらいいんだ!
私は2016年より地方のドラックストアで登録販売者の受験者の指導をしています。
漢方薬はみなさんが難しいと苦手意識をもってしまいますが。
実は漢方薬でも簡単に答えられる問題もあります。
今回の記事では、現役登録販売者講師の私が勉強会で使っている「色のイメージで覚える漢方一覧表」を公開します。
この漢方薬一覧表を使うと、細かい漢方薬の内容を覚えなくても、色と少ないキーワードだけで試験での正解を導き出せるようになります。
合格点まであと1点を積み上げるために、今回の記事が参考になると思います。
あなたに合った資格が見つかる‼
社会人や主婦の方の転職、キャリアアップ、収入アップに貢献できる資格を掲載中。
通信講座を比較・まとめて無料資料請求ができるサイト。
プロが作った教材なら短期間でラクラク合格も夢じゃない‼
漢方一覧表:イメージで覚えるから記憶に残る

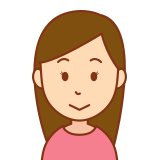
この表はよくある一覧表と何が違うのですか?
人間は外部からの情報の80%を視覚から得ていると言われています。
そこで、この漢方薬一覧表では、視覚イメージを使って覚えるられるように考えて作ってあります。
具体的には以下の特徴のとおりです。
- 3章の「〇〇の症状に用いられる薬」の項目順に分けられている。
- 各項目の中で上から下に体力がある順にならんでいる。
- 体力の強さが文字ではなく色で表現してある。
| 体力充実し | |
| 体力中程度以上 | |
| 体力中程度 | |
| 体力中等度又は | やや虚弱 |
| 体力中程度以下 | |
| 体力虚弱 | |
| 体力に関係なく | |
この漢方薬一覧表は、スマホなどを使い手軽に見ることができます。
表は横にスクロースがきるので、漢方薬名の部分をスクロースして隠し「症状+体力+キーワード」で漢方薬名が答えられるか?といった知識の確認にも使えます。
このページをブックマークしておけば、いつでもどこでも漢方薬の勉強ができます。
- あくまで個人利用にお使いください。
- データの再配布、再販売、複製、譲渡、自作発言 (著作権は放棄していません)
- 無断転載はお断りいたします。
| 症状 | 漢方薬名 | 体力 | キーワード | 副作用・その他 | カ | マ | ダ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 麻黄湯 | 初期・ふしぶしの痛み | カ | マ | ||||
| 風 | 葛根湯 | 汗をかいてない初期・肩こり | 肝機能障害・偽アルドステロン症 | カ | マ | |||
| 風 | 小柴胡湯 | 後期・舌に白苔 | インターフェロンで間質性肺炎 | カ | ||||
| 風 | 半夏厚朴湯 | 気分がふさぐ・喉のつかえ | カマダ無し | |||||
| 風 | 小青竜湯 | うすい水様の痰 | 間質性肺炎・肝機能障害・偽アルドステロン症 | カ | マ | |||
| 風 | 柴胡桂枝湯 | 中期から後期・腹痛・吐気・胃腸炎 | 間質性肺炎・肝機能障害・膀胱炎様症状 | カ | ||||
| 風 | 麦門冬湯 | 痰が切れにくく咽頭の乾燥感・しわがれ声 | 水溶痰の多い人:不向き | カ | ||||
| 風 | 桂枝湯 | 汗が出るかぜの初期 | 偽アルドステロン症 | カ | ||||
| 風 | 香蘇散 | 神経過敏・胃腸の弱い・血の道症 | 偽アルドステロン症 | カ | ||||
| 痛 | 麻杏薏甘湯 | 関節痛・神経痛・筋肉痛、・いぼ、手足のあれ | カ | マ | |||
| 痛 | 薏苡仁湯 | 関節や筋肉のはれや痛みがあるものの関節痛・筋肉痛・神経痛 | カ | マ | |||
| 痛 | 疎経活血湯 | しびれがあるものの関節痛 | カ | ||||
| 痛 | 釣藤散 | 慢性頭痛・高血圧 | カ | ||||
| 痛 | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 | 下肢の冷えが強く・月経痛 | カ | ||||
| 痛 | 呉茱萸湯 | 頭痛に伴う吐気・しゃっくり | |||||
| 痛 | 桂枝加朮附湯 | 汗が出、手足が冷えてこわばり・関節痛・神経痛 | どちらも動悸・のぼせ・ほてりの副作用が出やすい | カ | |||
| 痛 | 桂枝加苓朮附湯 | 手足が冷えこわばり・動悸めまい筋肉のぴくつきのある関節痛・筋肉痛 | カ | ||||
| 痛 | 芍薬甘草湯 | 筋肉の痙攣・こむらがえり・連用は避ける | 肝機能障害・間質性肺炎・虚血性心不全 | カ |
| 眠 | 柴胡加竜骨牡蛎湯 | 便秘などを伴う高血圧・神経症・小児夜泣き | 肝機能書・間質性肺炎 | ダ | |||
| 眠 | 抑肝散・抑肝散加陳皮半夏 | 怒りやすい・イライラ・歯ぎしり | 抑肝散:心不全を起こす可能性あり | カ | |||
| 眠 | 桂枝加竜骨牡蛎湯 | 興奮しやすい・小児夜泣き・眼精疲労 | 偽アルドステロン症 | カ | |||
| 眠 | 酸棗仁湯 | 心身が疲れ・不眠・精神不安 | 1週間位服用しても改善が見られないなら受診 | カ | |||
| 眠 | 加味帰脾湯 | 心身が疲れ・血色悪く熱感を伴う・貧血 | 偽アルドステロン症 | カ |
| 疳 | 小建中湯 | 小児虚弱体質・夜尿症・夜泣 比較的長期(1ヶ月位) | 体重辺りのグリチルリチン酸の量に注意 | カ | |||
| 桂枝加竜骨牡蛎湯 | 小児の夜泣きに用いる場合1週間くらい服用しても症状の改善が見られないときは服用を中止して専門家に相談 | カ | |||||
| 抑肝散 | カ | ||||||
| 抑肝散加陳皮半夏 | カ | ||||||
| 柴胡加竜骨牡蛎湯 | ダ |
| 咳 | 五虎湯 | 咳が強く出る | カ | マ | ||||
| 咳 | 麻杏甘石湯 | 咳が出て時に喉が渇く咳・小児喘息 | 間質性肺炎 | カ | マ | |||
| 咳 | 神秘湯 | 喘息・息苦しさ・痰が少ない小児の喘息 | カ | マ | ||||
| 咳 | 柴朴湯 | 小児の喘息・気管支喘息 | 肝機能障害・間質性肺炎・膀胱炎様症状 | カ | ||||
| 咳 | 半夏厚朴湯 | 嘔気・不安神経症・喉のつかえ・つわり | カマダ無し | |||||
| 咳 | 麦門冬湯 | 痰が切れにくい・咽頭乾燥間・水様性痰は不向き | 肝機能障害・間質性肺炎 | カ | ||||
| 咳 | 甘草湯 | 激しい咳・口内炎・痔 | 甘草のみの構成 | カ |
| 喉 | 白虎加人参湯 | 熱感と口喝の強い喉の渇き・皮膚のかゆみ | 比較的長期間服用 | カ | ||||
| 喉 | 響声破笛丸 | しわがれ声・咽頭不快 | カ | ダ | ||||
| 喉 | 桔梗湯 | 咳が出る扁桃炎・扁桃周囲炎 | カ | |||||
| 喉 | 駆風解毒湯・散 | 喉が腫れる扁桃炎・扁桃周囲炎 | うがいをしながら少しずつ服用 | カ |
| 胃 | 平胃散 | 食べすぎによる胃のもたれ・消化不良 | カ | |||||
| 胃 | 安中散 | 腹部は力がなくて・胃痛・胸焼け、げっぷ | カ | |||||
| 胃 | 六君子湯 | みぞおちがつかえて疲れやすい・貧血・胃下垂 | 肝機能障害 | カ | ||||
| 胃 | 人参湯 | 疲れやすく手足が冷えやすい胃腸虚弱 | カ |
| 腸 | 大黄牡丹皮湯 | 下腹部痛があり便秘しがちな人の月経不順 | ダ | |||||
| 腸 | 麻子仁丸 | 便が硬く塊状 | ダ | |||||
| 腸 | 桂枝加芍薬湯 | しぶり腹・腹痛・下痢・便秘 | カ | |||||
| 腸 | 大黄甘草湯 | 便秘・便秘に伴う頭重 | カ | ダ |
| 循 | 三黄瀉心湯 | のぼせ顔面紅潮・血の道症・高血圧・鼻血 | 鼻血は5~6回使用して改善ないなら相談 | ダ | ||||
| 循 | 七物降下湯 | 顔色が悪くて疲れやすく高血圧 | 15歳未満の小児への使用は避ける | |||||
| 循 | 苓桂朮甘湯 | ふらつき・神経過敏・水毒の排出 | 強心作用の生薬は含まれない | カ |
| 痔 | 乙字湯 | 便秘傾向のあるものの | 肝機能障害・間質性肺炎 | カ | ダ | |||
| 痔 | 芎帰膠艾湯 | 冷え性・出血傾向があ・胃腸障害がないもの | カ |
| 尿 | 竜胆瀉肝湯 | 尿の濁り・こしけ(おりもの) | カ | |||||
| 尿 | 牛車腎気丸 | 四肢が冷えやすく尿量減少・高齢者のかすみ目 | のぼせで赤ら顔の体力充実の人は不向き | |||||
| 尿 | 八味地黄丸 | 四肢が冷えやすく尿量減少or多尿・尿漏れ・夜間尿・高齢者のかすみ目 | ||||||
| 尿 | 六味丸 | 手足のほてり・排尿困難・口喝 | ||||||
| 尿 | 猪苓湯 | 口が渇くものの排尿困難・排尿痛 |
| 婦 | 桂枝茯苓丸 | のぼせて足が冷え・月経痛・打ち身 | 肝機能障害 | |||||
| 婦 | 桃核承気湯 | のぼせ便秘・月経時や産後の精神不安 | カ | ダ | ||||
| 婦 | 温清飲 | 皮膚はカサカサで色つやが悪い | 肝機能障害 | |||||
| 婦 | 五積散 | 更年期障害・月経痛・感冒 | 胃腸の弱い人・発汗の著しい人は不向き | カ | マ | |||
| 婦 | 温経湯 | 手足がほてり唇が渇く・手荒れ・こしけ | 胃腸の弱い人 | カ | ||||
| 婦 | 加味逍遥散 | のぼせ・いらだち精神神経症状・便秘傾向 | 肝機能障害・腸間膜静脈硬化症 | カ | ||||
| 婦 | 柴胡桂枝乾姜湯 | 貧血・神経過敏・更年期障害・かぜの後期 | 肝機能障害・間質性肺炎 | カ | ||||
| 婦 | 四物湯 | 産後・流産後の回復・しもやけ・しみ | ||||||
| 婦 | 当帰芍薬散 | 冷性・皮膚乾燥・産前産後・流産後の障害(めまい・むくみ) |
| 皮 | 消風散 | 痒みが強く分泌物が多・局所熱感 | カ | |||||
| 皮 | 茵蔯蒿湯 | 尿量少なく便秘するものの蕁麻疹・口内炎 | ダ | |||||
| 皮 | 十味敗毒湯 | 化膿性皮膚疾患・水虫 | カ | |||||
| 皮 | 当帰飲子 | 冷え性・皮膚乾燥・湿疹・皮膚炎(分泌物少) | カ |
| 鼻 | 葛根湯加川芎辛夷 | 鼻詰・蓄膿症 | カ | マ | ||||
| 鼻 | 荊芥連翹湯 | 皮膚が浅黒く手足の裏に脂汗・鼻炎・ニキビ | 肝機能書・間質性肺炎 | カ | ||||
| 鼻 | 辛夷清肺湯 | 濃い鼻汁・熱感をともなうものの鼻づまり | 肝機能書・間質性肺炎・腸間膜動脈硬化症 | |||||
| 鼻 | 小青竜湯 | うすい水様の痰・アレルギー性鼻炎 | 間質性肺炎・肝機能障害・偽アルドステロン症 | カ | マ |
| 漢 | 大柴胡湯 | 脇腹からみぞおちが苦しい、便秘・胃炎 | 肝機能書・間質性肺炎 | ダ | ||||
| 漢 | 防風通聖散 | 腹部皮下脂肪多く便秘がち・高血圧 | 肝機能書・間質性肺炎・偽アルドステロン症 | カ | マ | ダ | ||
| 漢 | 黄連解毒湯 | のぼぜ・顔が赤くイライラ・鼻血・二日酔い | 肝機能書・間質性肺炎・腸間膜動脈硬化症 | |||||
| 漢 | 清上防風湯 | 赤ら顔・のぼせ・ニキビ | 肝機能書・偽アルドステロン症 | カ | ||||
| 漢 | 防已黄耆湯 | 水太り・肥満・多汗・むくみ | カ |
| 滋 | 十全大補湯 | 病後・術後の体力低下・貧血・手足の冷え | 肝機能障害 | カ | ||||
| 滋 | 補中益気湯 | 病後・術後の虚弱・感冒 | 肝機能障害・間質性肺炎 | カ |
| 外 | 紫雲膏 | しもやけ・ひび・あかぎれ・うおのめ | ||||||
| 外 | 中黄膏 | 打ち身・捻挫 |
一度に全ての内容を覚えなくても大丈夫です、分かりやすいもの・覚えやすいものから少しずつ覚えていきましょう。
登録販売者試験の3章、漢方薬の問題は「名前・〇〇の症状に用いられる薬・色(体力)・キーワード」これが覚えられたらかなりの確率で正解を導き出せるようになるはずです。
漢方一覧表PDF版
紙ベースの漢方薬一覧表のほうが使いやすいという方は、下のボタンからPDFデータ版がダウンロードできます。
プリントアウトして毎日の勉強に使ってください。
漢方の覚え方のコツ:しばり表現について

漢方薬を苦手と感じる理由の一つは、漢字の長い名前が難しいこともありますが、それ以外にも漢方薬独特の「しばり表現」が理解しづらいことも原因となっています。
漢方薬は西洋薬と異なり、同じ症状でもそ人の体力や体格によって異なる薬を使用します。
例えば、鎮痛剤を飲む人の体力や体格によって、バフリンAかイブAかを使い分けるようなものです。
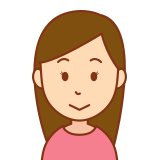
西洋薬になれた私達にはイメージしづらいですね。
簡単に言えば、しばり表現とは「体力が〇〇で体格が△△な人で□□の症状なら、この薬が効きますよ」と、薬の効果が期待できる人に一定の条件があることを指します。誰が飲んでも効くわけではありません。
注意すべき点は、その薬に合わない体力や体格の人が飲んだ場合、効果が出ないばかりか副作用が発生しやすくなることがあるということです。
このように重要なことなので、漢方薬の広告では原則としてしばり表現を省くことは認められていません。店頭で漢方薬を勧める場合、この「しばり」を理解していないと大変なことになる可能性があるため、試験では必ず「しばり」について出題されます。
まずは簡単に答えられる問題から覚えよう

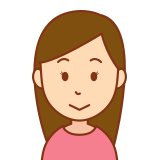
最初に言っていた「簡単に答えられる問題」ってどれですか?
まずは簡単に正答できる問題パターンを紹介します。
ただし、これは漢方薬の問題を捨てるぐらいなら、最低限覚えてほしい内容です。
とりあえず、以下のような問題が正答できるようになってから次の段階に進めば良いでしょう。
「名前+〇〇の症状に用いられる薬」をセットで覚える
漢方薬一覧表は、あいうえお順などではなく、症状ごとに薬をまとめて表記しています。これは「名前+〇〇の症状に用いられる薬」をセットで覚えるためです。
名前を見ただけで細かい薬の内容まではわからなくても、「確か婦人薬にあったな…」と思い出せればOKです。
実際の問題を見てみましょう。
問 次の1~5で示される漢方処方製剤のうち、「女性の月経や更年期障害に伴う諸症状の緩和」に用いるものはどれか。
1 十味敗毒湯
2 小青竜湯
3 当帰芍薬散
4 乙字湯
5 猪苓湯
設問の内容は「婦人薬はどれか?」ということになりますが、漢方一覧表を見ていただければわかる通り、選択肢の1~5の中に婦人薬は3の『当帰芍薬散』しかありません。
このような問題も実際の試験にかなり頻繁に出題されます。
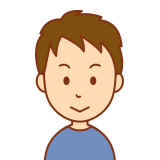
めちゃくちゃ簡単じゃないですか。
ただし、漢方薬には似たような名前の薬もたくさんあります。
- 柴胡桂枝湯・・・かぜ薬
- 柴胡桂枝乾姜湯・・・婦人薬
- 桂枝加竜骨牡蛎湯・・・小児夜泣等
- 桂枝加朮附湯・・・鎮痛薬
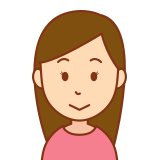
うぁぁもういいです。
漢方薬を名前だけで「あいうえお順」などで覚えると、上記のような薬は頭の中でごちゃ混ぜになってしまいます。
最初は少しずつで良いので、「名前+〇〇の症状に用いられる薬」で覚えられるものを増やしていけば良いでしょう。
同じ症状に用いられる漢方薬で同じ色(体力)が無いものを覚える
漢方一覧表ではしばり表現の体力を色で分けて表現しています。
「名前+〇〇の症状に用いられる薬」を覚えたら、次に漢方薬一覧表で同じ症状に用いられる薬の中で同じ色(体力)が無いものから覚えます。同じ色がなければそれ以上の細かな内容はとりあえず後回しでも正解は導き出せます。
例えばかぜ薬の項目で同じ色が無いものは下の画像の通りです、超頻出問題になる「麻黄湯」「葛根湯」は同じ色がありません。
| 症状 | 漢方薬名 | 体力 | キーワード | 副作用・その他 | カ | マ | ダ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風 | 麻黄湯 | 初期・ふしぶしの痛み | カ | マ | ||||
| 風 | 葛根湯 | 汗をかいてない初期・肩こり | 肝機能障害・偽アルドステロン症 | カ | マ | |||
| 風 | 麦門冬湯 | 痰が切れにくく咽頭の乾燥感・しわがれ声 | 水溶痰の多い人:不向き | カ | ||||
実際の問題を見てみましょう。
問 第1欄の記述は、かぜ(感冒)の症状緩和に用いられる漢方処方製剤に関するものである。該当する漢方処方製剤は第2欄のどれか。
第1欄
体力中等度以上のものの感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛みに適すとされるが、体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)、胃腸の弱い人、発汗傾向の著しい人では、悪心、胃部不快感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。
まれに重篤な副作用として肝機能障害、偽アルドステロン症を生じることが知られている。
第2欄
1 薏苡仁湯
2 呉茱萸湯
3 小柴胡湯
4 小建中湯
5 葛根湯
問題では「第1欄から該当するかぜ薬を選べ」とありますが、第1欄の「体力中程度以上」の部分まで読んだ段階で、かぜの症状に用いられる漢方薬は『葛根湯』しか無いはずですから第2欄の5が正解だと分かります。
最初からすべてを完璧に覚えようとしない
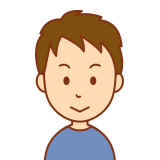
過去問で「重篤な副作用」や「カンゾウが含まれている」とか、イロイロな問題がありますが
最初に書いた通り、これは漢方薬の問題を解くために最低限覚えてほしい内容です。
どの章でも言えることですが、最初からすべてを完璧に覚えようとしなくて大丈夫です。
完璧を求めすぎると、勉強が前に進まなくなってしまいます。
登録販売者試験では、完璧に答えられる問題を10個作るより、7割ぐらい正答できる問題を50個作ったほうが合格に近づけます。
例えば、同じ症状に用いられる漢方薬が5つあるなら、そのうちの2つをはっきりと覚えておけば、2択や3択まで絞れるようになります。最低限、試験に合格することが目的なら、それでも構いません。
欲張らず、一度に漢方薬の「名前+〇〇の症状に用いられる薬」を覚え、その次に頻出または分かりやすい漢方薬の「体力」について少しずつ覚えていけば良いです。
おすすめ書籍:参考書のサブテキストとして
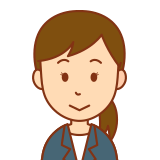
参考書ではなく漢方薬だけでおすすめな参考書とかありますか?
大人から子供まで大人気「漢方薬キャラクター図鑑」
私の勉強会参加者で漢方薬のサブテキストとして好評なのがこの『漢方薬キャラクター図鑑』です。SNSで登録販売者試験の勉強をしている人がオススメしているのも良く見かけます。
難しい漢字の羅列は覚えるのが苦手な人にかわいいキャラクターのイメージで薬を覚えることができます。見開き左側ページにキャラクター右側ページに薬の説明となっていてとても見やすい構成です。
登録販売者試験のための本では無いので必ずしも合格するのに十分な知識が学べるというわけではありませんが。視覚からのイメージで薬を学ぶと言う意味では私の漢方一覧表と同じ発想だと思います。
- キャラクターの体力に合わせて漢方一覧表と同じ色を塗ると学習効果が急激にUPします。
- 本に載っていないキャラクターを自分で勝手に妄想してしまいナゼか勉強している状態になります。
- 疲れて勉強をしたくない日に、チョット目を通してるといつの間にか勉強になってしまいます。
意外と漢方薬の理解が深まりますよ。
こんなのが欲しかった!3章最短攻略に特化した参考書「医薬品暗記帳」
みんなが苦戦する3章の救世主、まさに「こんなのが欲しかった!」と言う参考書です。あまりの人気でしばらく各ネット販売サイトでは在庫切れとなり入手困難となっていました。
内容としては3章でたくさん出てくる成分を重複記述なしの超効率化掲載を実現、勉強のムダ無くして最短ルートで3章の成分・生薬・漢方薬を学習する事ができます。
特に生薬・漢方薬はイラストが豊富に使われていますが、驚いたことに漢方薬1つ1つのしばり表現に合わせた患者さんがのイラストが登場します。
例えば小柴胡湯なら『体力中程度で、ときに脇腹(腹)からみぞおちあたりにかけて息苦しく、食用不振や口に苦味があり、舌に白苔がつくもの』のしばり表現にあった人物がイラストで登場します。
こちらも視覚からのイメージで薬を学ぶと言う意味では私と同じ考えと言えるのでは無いでしょうか。
- 無駄なく最速で学習できるので3章の勉強が間に合わないと思っている方に。
- 各成分の頻出度が表示されているので試験に出やすいものから学習したい方に。
- 「使用上の注意」も一緒に記載されているので3・5章の副作用や注意することが苦手な人に。
- 生薬・漢方薬はイラストがたくさん載っているので文章だけでは覚えられそうに無い方に。
- 3章に特化した参考書なので今使っている参考書の3章の記述がわかりにくいと考えている方に。
この参考書は試験に合格したあと店頭に立ったときも使える知識がたくさん詰まっています、ずっと手元に置いて長く使い続ける事ができる参考書になるはずです。